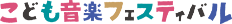こども音楽フェスティバル 2025 【DAY3】レポート

フェスティバル3日目、5月5日(月・祝)の様子をレポートします!
◆Concert for KIDS ~0才からのオーケストラ~
5月5日(月・祝)、『こども音楽フェスティバル 2025』もいよいよ3日目で折り返しとなりました。この日は大ホールの「Concert for KIDS ~0才からのオーケストラ~」からスタートです。
鷲尾麻衣さん演じるモーツァルトと、吉川健一さん演じるパパゲーノの掛け合いを交えながら、オーケストラの作品が次々と演奏されます。ブラームスの「ハンガリー舞曲」では、なんと客席の皆さんも指揮で参加! 指揮者、園田隆一郎さんのコーチで2拍子をマスターした観客と、東京フィルハーモニー交響楽団の思いがけないセッションが誕生しました。赤ちゃんも大人も、全身で音楽を体験できたのではないでしょうか。
◆ピーターとオオカミ ~アニメーション付きコンサート~
ブルーローズ(小ホール)では、「ピーターとオオカミ」のアニメーション付きコンサートが開かれました。米田覚士さん指揮のもと、AOIアンサンブルがモーツァルト「フィガロの結婚」の序曲を披露したら、楽器紹介の時間。司会の神崎ゆう子さんとアンサンブルの面々がたっぷりレクチャーしてくれます。神崎さんの名調子に、子どもたちも積極的なリアクションが絶えません。
チャイコフスキー「くるみ割り人形」の〈小序曲〉でお気に入りの楽器の音色を堪能して、いよいよ「ピーターとオオカミ」の始まり。カラフルでかわいらしいキャラクターが生演奏と一緒に動き回ります! アヒルがオオカミに丸呑みされてしまうシーンでは、会場からどよめきが起こりました。朗読と楽曲、そして映像が織りなす物語に、来場者は最初から最後まで釘づけでした。
◆インクルーシブなワークショップ
『こども音楽フェスティバル 2025』では「Music for All」を掲げ、障がいの有無や年齢、環境などにかかわらず、だれもが楽しめるインクルーシブな取り組みを実践しています。その一環として、連日さまざまなワークショップが開催されています。
「音のかけらでコラージュしよう♪」ワークショップでは、参加者は、自分だけのトートバッグ作りにチャレンジします。赤や青、色とりどりの模様がプリントされたシートを、自由に切り貼りしていきます。真剣な顔つきで、シートを慎重に動かす子どもたちの指先から目が離せません。最後の仕上げは大人の出番。ヒートプレスで、バッグとシートをしっかりくっつけて完成です!
ここで使われたきれいなシートのイラストは、難聴の子どもたちや支援学校に通う子どもたちが制作した作品からできています。子どもたちの「コエのカタチ」「オトのカケラ」が、また別の子どもたちの作品に繋がる。アートと音楽の営みを感じる、すてきな空間でした。
3日目には、「祝い花」を用いてキーホルダーを作るワークショップ「コンサートを彩ったお花でつくるオリジナル・キーホルダー!」に参加しました。ライブやコンサートなどのイベントで廃棄されている花々を再利用する試みです。今回は、実際にサントリーホールに贈られた祝い花を使います。
カゴいっぱいに詰められたドライフラワーに、子どもたちは開始前から興味津々! 透明なケースにできるだけお花を詰め込んで、ぎゅっとフタをしたら、白いペンで自分の名前や模様を描いてできあがり。小さなお花をたくさん入れるのか、大きなお花を折ったり畳んだりして収めるのか。シンプルな工作だからこそ、素材の選び方やペンの描き込み方、ひとつひとつに個性が表われる、見ているだけでワクワクするキーホルダー作りでした。
◆ぱんだウインドオーケストラ Presents ファンタスティック! こぱんだウインズ
吹奏楽シーンに新風を吹き込んでいる「ぱんだウインドオーケストラ」から、7人が集結した「こぱんだウインズ」のコンサート。それぞれの楽器におけるスタープレイヤーが勢揃いとあって、吹奏楽をやっている小中学生が多く来場していました。
ぱんだウインドのコンサートではおなじみの前久保諒作曲「PANDASTIC!!」を全員で演奏してのオープニング。ブルーローズいっぱいに鳴り響く金管六重奏+ピアノの響きは迫力たっぷりです。「大人数じゃなくても吹奏楽は楽しい」というコンサートマスターの上野耕平さんの言葉に続き、ひとりずつソロ曲を披露していきます。
トップバッターはトランペットの鶴田麻記さん。アーバンの「〈輝く雪の歌〉による変奏曲」は主題が変奏されていくにつれ難易度が上がっていきますが、完璧なテクニックで聴かせてくれました。トロンボーンの山下純平さんは、ダヴィッドの「トロンボーン小協奏曲」より第1楽章。さまざまに移り変わる曲想から、トロンボーンの豊かな響きと繊細な表情が伝わってきます。テューバの芝宏輔さんは、レベデフの「演奏会用アレグロ」より。煌びやかなピアノと、それを包み込むようなテューバの深い響きが溶け合います。
ユーフォニアムの佐藤采香さんは、スパークの「パントマイム」より。ゆったりと美しく歌う前半と、スピードアップして躍動的な後半のコントラストが鮮やかな曲を通して、ユーフォニアムという楽器の魅力を存分に味わうことができました。ホルンの濵地宗さんは、グラズノフの「夢」。ホルンってこんなにも情感豊かな表現ができるんだと驚くばかりです。そして最後はサクソフォーンの上野耕平さんによる、デュボワの「組曲形式による性格的小品集」より〈パリジェンヌ風に〉。スリリングでユーモラスな曲を、客席との会話を楽しむように演奏する上野さんの姿が印象的でした。
締めはふたたび全員の演奏で、「アメイジング・グレイス」(芳賀傑編曲)と、ムソルグスキー(中村匡寿編曲)の「展覧会の絵」より。それぞれの楽器の音色の違いを知ったうえでアンサンブルを聴くと、重なり合う響きの美しさがよりいっそう感じられます。「展覧会の絵」ではオーケストラも顔負けの音圧と表現力に圧倒されました。
◆Piano+(ピアノ・プラス)
3日目の大ホール公演の最後は、当フェスティバルのコンサート・プログラマーを務めるピアニストの角野隼斗さんがナビゲートする「Piano+」。ピアノとさまざまな楽器によるアンサンブルの楽しみを発見するコンサートです。
角野さんと司会の松本志のぶさんがステージに登場し、「こんにちは」と呼びかけると、「こんにちは〜!」と子どもたちの大きな声が返ってきて、あらためて角野さんの人気の高さを感じました。ピアノをがんばっている子にとって憧れの存在なのでしょう。
- ©平舘平/サントリーホール
はじめはピアノ・ソロでショパンの「華麗なる大円舞曲」から。どこまでも軽やかで優雅なワルツにうっとり。大きなホールでたったひとりで演奏するとき、角野さんは楽器やホールと一体化することで、2,000人のお客さんに響きを届けているのだそうです。
続いては、ピアノ+管楽器。読売日本交響楽団から、オーボエ(荒木奏美)、クラリネット(金子平)、ファゴット(井上俊次)、ホルン(松坂隼)という4人の管楽器奏者が登場し、ベートーヴェンの「ピアノと管楽器のための五重奏曲」より第3楽章を角野さんと共演します。はずむようなメロディとあたたかな響きのなかで、なごやかな会話を楽しんでいるかのよう。ほかのプレイヤーの演奏に応えて当意即妙に表情を変えていく、角野さんのアンサンブル能力の高さを感じさせる演奏でした。
ピアノ+弦楽器では、同じく読響からヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの弦楽アンサンブルと、ピアソラの「ブエノスアイレスの春」を共演。前の曲とは打って変わって、ソリッドな弦のアンサンブルを、角野さんが強力なグルーヴで牽引していきます。
そしてラストは全員が登場して、ピアノ+オーケストラ。なんと今日は角野さんの弾き振り(指揮をしながらピアノを弾く)によるガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」です! 「オーケストラの皆さんとジャズのセッションをしているように演奏したい」と演奏前に語っていた角野さんですが、そんな彼に触発されたかのようにオーケストラも自由で楽しそう。角野さんのピアノの上で踊っているように感じられる場面もありました。そうかと思えば、カデンツァ(ソロで即興的な演奏をする部分)は角野さんの独壇場。ニューヨークのバーでラグタイムを聴いていたかと思えば、摩天楼を見下ろすラウンジで優雅にシャンパンを――そんな光景が広がります。
その後はふたたびオーケストラが戻ってきて、大きく伸縮してクライマックスへ。見事に弾き振りという大役を果たした角野さん。「ラプソディー・イン・ブルー」という作品の面白さを隅から隅まで知り尽くしているからこそ、自在に遊ぶことができるのでしょう。
「Concert for KIDS ~0才からのオーケストラ~」と「Piano+(ピアノ・プラス)」はアーカイブ配信でも視聴できますので、会場に行けなかった方も、コンサートの余韻を味わいたい方も、ぜひ配信でお楽しみください。
取材・文/加藤綾子・原典子